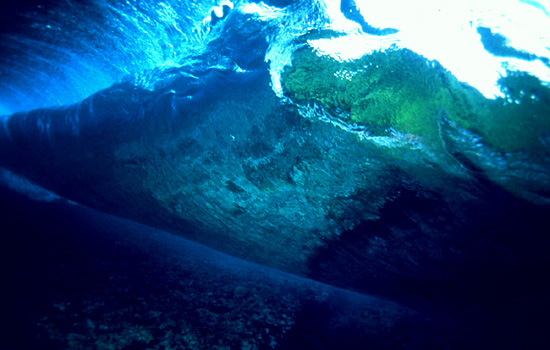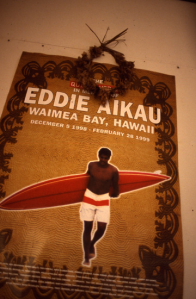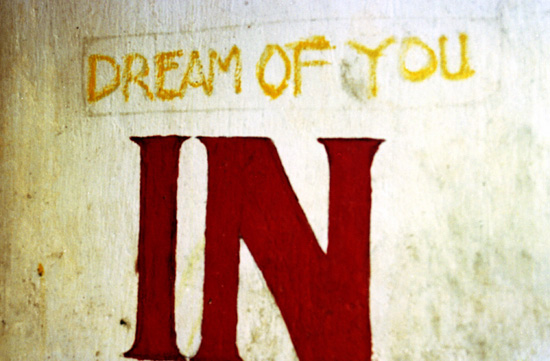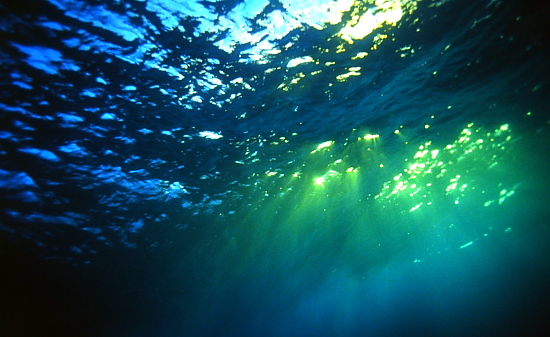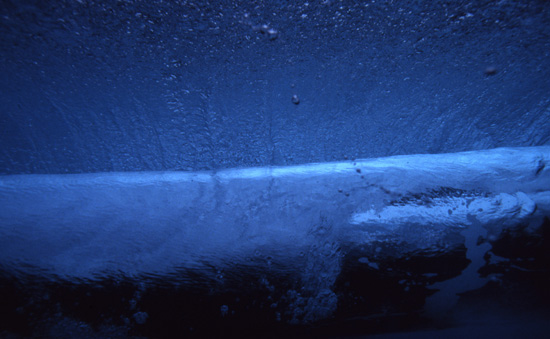表層しか知らないでいた。
波という言葉は、あたかも一つの「物」のように単一で、物質的な物言いだ。
明治政府が西洋化をおしすすめ、仏像焼きながら作った造語「自然」しぜん。
本来は仏教用語「自然」じねんを、ネイチャーに利用しただけ。
と禅に深く関わる書道家大橋陽山氏から聞いた。
ジャンクな町と地球を都合よく線を引く為、つけた言葉だ。
実際に触れてみないとわからない。
実際にその場にいないとわからない。
いや、既に何が良くて、悪いのかを本当は皆理解できている。
もっと言えば「良い事」ではなく、「当たり前」の事を人は知っているはずだ。
太陽がいかに大切で、地に足がつく大地が大切なのかを知る様に。
教わる事でもないわけです。
笑い話だが核ってなんでしょう?
この地球に、宇宙にないものを人間が作ったのだから、分解など出来る訳が無い。
「除染」という「巧妙な」言葉ほど、「自然」と同じく欺瞞に満ちた言いまわしはない。
実際には丸い地球の川から海へ、海から山へ、よその國へいくだけ。
このやっかいものは、半永久的に地球や生命を傷つけながら動き回るだけのお話。
でも核は莫大なお金になるらしいから、好きな方が多いのですね。
どこかの企業やエコビジネスが言う「自然」こそ「不自然」だとわかる日がくればいい。
意識がその向こう側と繋がり、気づいた時に、町や海岸におちているゴミを拾っている。
地球を知った様な顔の科学者やメディアの、薄くて馬鹿なお話に耳を傾ける時間があれば
まづは「自然」しぜんへ行きましょう。
この地球をもっと好きになります。
そのうちきっと気づく日がきます。
雨のフィジーの離島の300m程沖
地球の海の崖の中で。