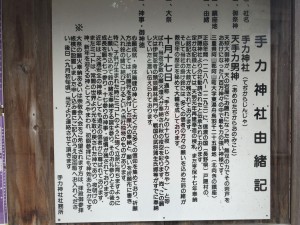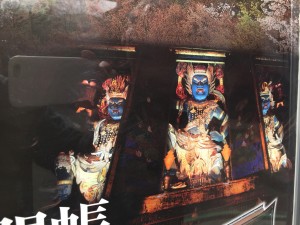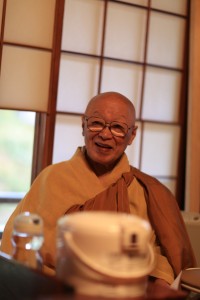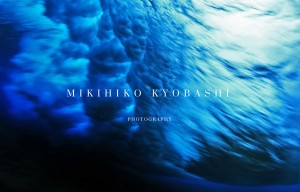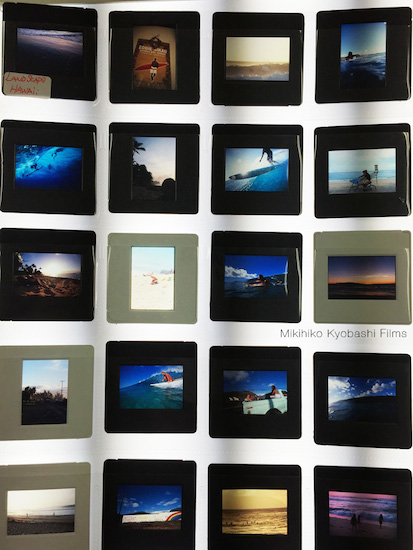I came to the mountains of rainy Yoshino
Now 1,400 years ago
Before Giyoja Enno who trained himself/herself at the waterfall of nearby mountains
I enshrine the Zao Gongen of a Japanese god that appeared
It is a beginning of mountaineering asceticism ancestor
Mountaineering asceticism is like Aminizumu, and it is folk belief
It was created while occurring extremely naturally, and blending with esoteric Buddhism and Buddhism
It is the method of one earth talk beyond the religion
The fact that includes the time when it is older than the Buddhism of the import thing
What Nakamura kept a fruit, and tested “a mountaineering ascetic”
The course of art and the manners that I right mastered by an experience and the experience in own mountains
It is mountaineering asceticism
I right say the school of these days to let you think with a head
A culture fish preserve is the splendid earth school which is the other dimension
For Japanese a population of 400,000 people
The fact that the 170,000~8 all people had a mountaineering ascetic
Syugenjya Nakamura says both the training and the experiment
It is mountaineering asceticism to master experience and an experience in mountains
In other words, it is a practitioner of the realism
The Meiji government pollutes westernization
I do the mountaineering asceticism abolition,
By false words called nature
Draw a line on a human being and the earth; and 150 years
It is the reason why aftereffects remain to the Japanese now
On a town and the earth
I draw a line by the word nature conveniently
I kept it away from the fear and importance
An excessive convenient living
Of the distance of talks and the bodily sensation with the earth
It is the reason that made a trench
In the neighborhood without nature
As for the present times to buy a flowerpot
May it be an important thing?